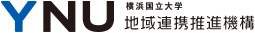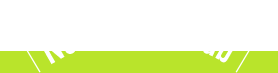都市空間研究会
活動の目的と内容
都市空間研究会は都市イノベーション学府・研究院を拠点にした平成29-30年度、平成31年度/令和元年度-2年度の部局長戦略的経費、そして「〈都市の未来像〉の新しいパラダイムを構築する書籍刊行と研究拠点の形成」事業による令和2年度の学長戦略経費や令和元年度から5年度の「Next Urban Lab」ユニットとして支援を受け、学内外の学生と教員、そして地域に開かれた研究教育活動を持続させてきた。研究会の継続的な討議は書籍(吉原直樹・榑沼範久/都市空間研究会編『都市は揺れている 五つの対話』、東信堂、2020年)として世に問い、岩崎稔氏(元東京外国語大学理事・副学長)による書評が『週刊読書人』(2020.08.07)に掲載されるなど反響があった。以後も都市空間研究会は学外の研究者などとも交流を深め、講演会や地域のフィールドワークを行ってきたが、令和7年度は総括責任者や学内分担者が参画する総合学術研究院(豊穣な社会研究センター及び生物圏研究ユニット)とも連携しながら、生物圏を含めた日本列島の「内陸地域のつながり方」を研究調査し、地域課題の発掘を行う計画である。
地域課題解決・地域連携推進にどのように貢献するか
内陸地域として特に想定するのは、最大の「海なし県」長野県/信州である。総括責任者の居住する地域であり、学内分担者(多和田)が本学着任前に勤務していた飯田市歴史博物館のある地域でもある。二十世紀の日本の経済成長を支えた太平洋ベルトの工業地帯からも、近世に北前船が活躍した日本海海運からも離れていたが、遥か縄文時代から多種の事物や文物を携えた人びとが沿岸地域からも都からも集合する「都市的」地域でもあった。近代でも西田幾多郎を中心とする「京都学派」の哲学者たちが繰り返し訪れ、重要な講演をした地域でもある。しかしこうした歴史を忘れるとき、ここもただの「地方創生」の対象になってしまう。都市空間研究会では、この「都市的」内陸地域を縄文時代から近代に至る「つながり方」の宝庫、そして文化圏・生物圏も含めた多種的な「里山都市群」として新たに分析しなおし、つながり方の地図を描きなおすことで、大都市従属の「地方創生」を超えた、内陸地域ルネサンスのための知識基盤の形成に貢献する。
メンバー
【活動代表責任者】
榑沼 範久 (都市イノベーション研究院・総合学術高等研究院)
【学内分担者】
カルパントラ ファビアン (都市イノベーション研究院)
齊藤 麻人 (都市イノベーション研究院)
彦江 智弘 (都市イノベーション研究院)
三浦 倫平 (都市イノベーション研究院)
守田 正志 (都市イノベーション研究院)
多和田 雅保 (教育学部・総合学術高等研究院)
【学外協力者】
吉原 直樹 (東北大学名誉教授)
(担当:地域連携推進機構)
地域連携推進機構
「ネクスト・アーバン・ラボ」ユニット 一覧