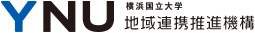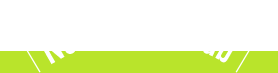川崎市との協働にもとづく生活相談のデータ分析
活動の目的と内容
2024年度の1年間にわたり、川崎市と協働で受けた生活相談に関するデータを、学生たちがチームを組んで話し合いながら分析するアンサンブル・プログラミングを用いて整理・分析をしてきた。雇用相談・生活相談について窓口となっている「だいJOBセンター」から2016~2023年の8年間の相談記録に関するデータ提供を受け、現在の課題についてフィードバックをした。本取り組みを、2025年度も継続していきたいと考えている。本取り組みには3つの目的がある。
(1) 自治体の政策方針検討についてデータ分析の貢献をすること: 現状は、生活福祉の職員がExcelなどを用いて生活相談利用状況についてレポートをまとめていた。しかし、この方法ではデータの結合などが困難なため、解析できていない側面があった。データサイエンスの知識と技術を活かして、分析の一助となることを目指している。
(2) 学術的な知見を得ること: 生活相談サービスについて、過去8年間の長期データが蓄積されており、このデータを分析して生活困窮に関する学術的知見を得たいと考えている。
(3) データ分析を学ぶ学生が技能と姿勢を学ぶ場をつくること: データサイエンスの授業などでデータ分析プログラミングの知識を学んでも、実践的な経験をつまなければ、実際にプログラミングを任せられるほどまでは習得できない。定期的にグループで話し合いながらプログラミングを進めることによって、技能の習得を目指す。
地域課題解決・地域連携推進にどのように貢献するか
生活福祉は、住みやすい地域づくりのために重要な政策領域である。自治体は行政の取り組みを通じて、今までデータを蓄積しているが、十分に分析できなかった。そこで、データサイエンスに関する学術的知見と技能を活かして、地域政策への理解を深める貢献をしたいと考えている。例えば、生活相談に関する過去8年間のデータを分析して、現在2つの側面を理解したいと考えている。(1)「生活相談サービスを受ける受給者の支援期間が長期化している」という印象を多くの生活相談員が持っている。このような傾向が実際にデータから確認できるか、長期データを結合して検証している。(2)相談者の精神衛生に関する現状を定量分析したいと考えており、テキスト分析の手法を用いて、相談内容の傾向を分析したい。これら2つの分析内容は、データサイエンスの知識がなければ困難であり、地域の政策方針検討への貢献となると考えている。
メンバー
【活動代表者】
古川 知志雄 (国際社会科学研究院)
【学内分担者】
相馬 尚人 (国際社会科学研究院)
【学外協力者】
深井 太洋 (学習院大学 経済学部)
(担当:地域連携推進機構)
地域連携推進機構
「ネクスト・アーバン・ラボ」ユニット 一覧