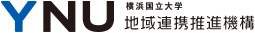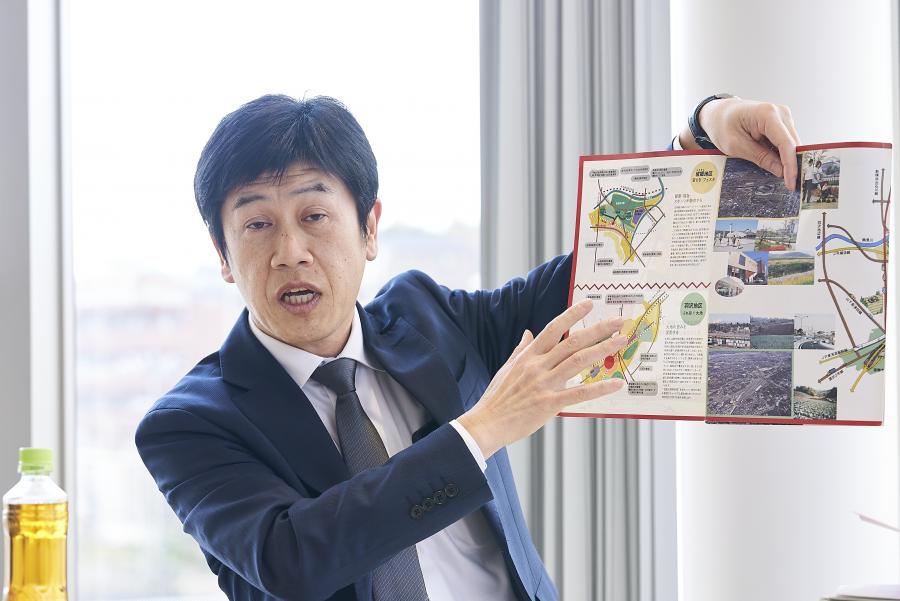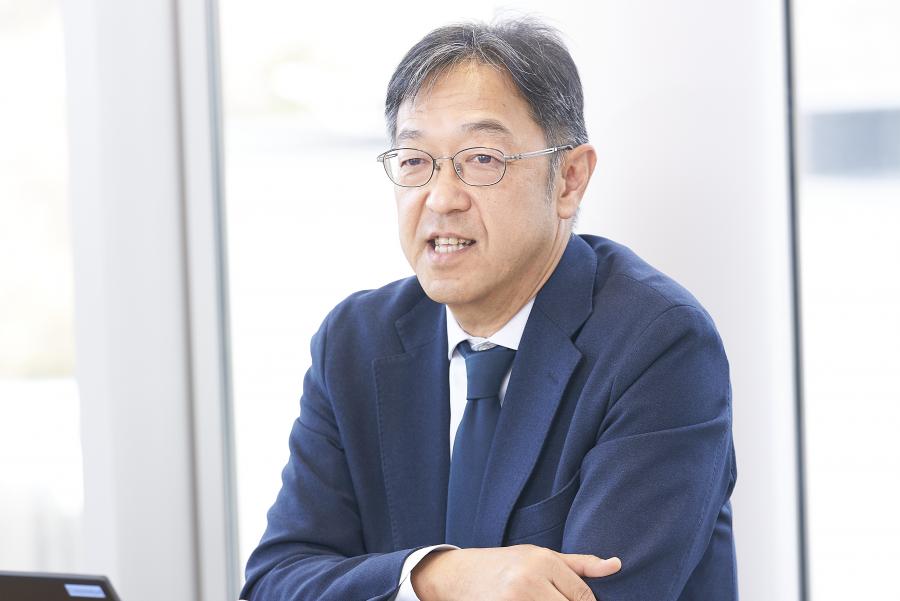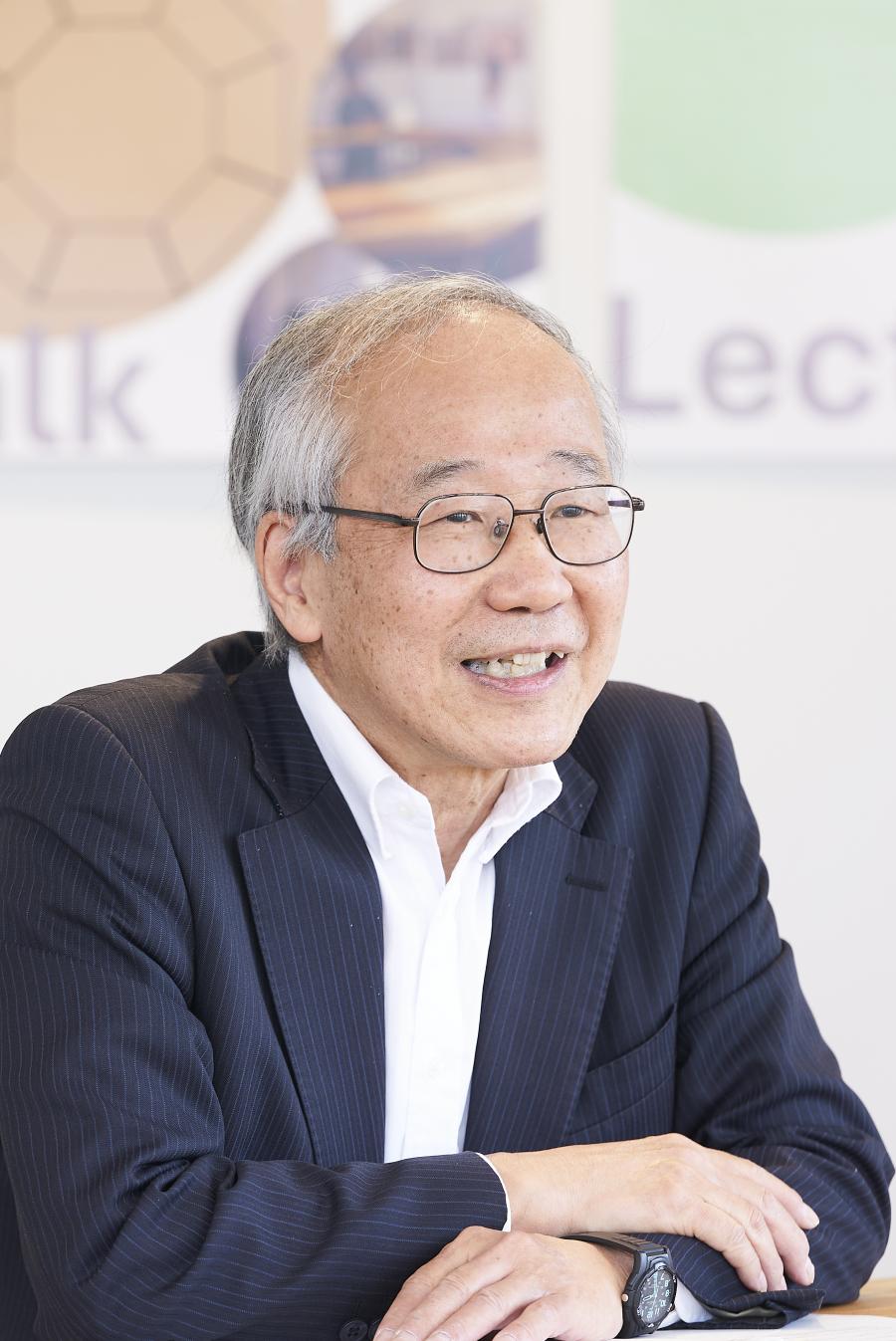新しい駅を、新しい「まち」に。「YNU BASE HAZAWA」からはじまる産学官民の挑戦
「YNU地域連携最前線」では、自治体・企業等との連携事業の中から注目される活動をピックアップして発信しています。第10回目は、2024年10月に羽沢横浜国大駅前にオープンしたサテライト施設「YNU BASE HAZAWA」について、地域連携推進機構・学長特任補佐の高見澤実名誉教授、神奈川区区政推進課長の佐藤一道様、横浜市都市整備局都心再生課担当課長の宮本康司様、寺田倉庫株式会社執行役員の田嶋拓也様、株式会社相鉄ビルマネジメント取締役・ 齋賀幸治様にお話を伺いました。聞き手は地域連携推進機構長の田中稲子教授です。
産学官民の連携で生まれ変わった「羽沢地区」
──本日はお集まりいただきありがとうございます。まずは自己紹介を兼ねて、「どのような形でこの羽沢地区に関わっておられるのか」を伺えますでしょうか。
宮本:横浜市都市整備局都心再生課の宮本です。私どもは1999年に「新横浜都心整備基本構想」を策定し、新横浜都心を構成する新横浜、城郷、新羽、羽沢の4地区の都市整備を進めてきました。なかでも羽沢横浜国大駅の開業は、この基本構想の目玉のひとつです。その象徴となるYNU BASE HAZAWAもついにオープンとなり、まさにこのエリアが動き出すタイミングだと感じています。
佐藤:神奈川区区政推進課の佐藤です。地域住民にとっても今回の新駅誕生は大きなニュースです。そこで生まれる新たなニーズをうまく拾い上げ、政策やイベント等に反映していけたらと考えております。

神奈川区区政推進課長 佐藤一道様
田嶋:寺田倉庫で不動産事業に携わっている田嶋と申します。弊社はもともと1960年代よりこの羽沢地区に営業所を構えており、10棟ほど倉庫を所有していました。新駅の計画がスタートして以降は、地権者として区画整理や開発に取り組んでおります。特にYNU BASE HAZAWAの入居する「HAZAAR」は、寺田倉庫初の複合商業施設ということもあり、非常に力が入っております。私自身も実は羽沢出身でして、個人的にも本件は思い入れの強いプロジェクトです。
齋賀:相鉄ビルマネジメントの斎賀です。もともとは相鉄アーバンクリエイツに在籍しており、新駅周辺の開発プロジェクトにも深く携わっておりました。現在は「HAZAAR」の物件マネジメント担当として、テナントさんの開業準備などを進めているところです。
高見澤:2024年3月まで横浜国立大学に在籍しておりました高見澤です。羽沢地区については、長らく「見守り役」のような立場で開発の変遷に立ち会ってきました。私が本学に着任したのは1986年ですが、交通の不便さに驚いたのを今でも覚えています。こうして都心直通の新駅ができ、新たなまちづくりが始まるというのは、本当に画期的な変化に感じられますね。
大学を「地域資源」として活かす
──続いて、YNU BASE HAZAWA開設に至る経緯として、新駅誕生までの流れを簡単に振り返っておきたいと思います。まず、先ほども宮本さんからお話がありましたが、1999年に横浜市が発表した「新横浜都心整備基本構想」を皮切りに、羽沢地区の再開発がスタートしました。
その後、新駅や鉄道乗り入れに関する国の計画発表を経て、2011年に「羽沢駅前地区まちづくり検討会」が設立されます。このあたりの経緯について、何か補足はございますでしょうか。
齋賀:新駅誕生のきっかけとなったのは、2005年に制定された国土交通省の「都市鉄道等利便増進法」です。はじめに相鉄・JR直通線の計画がスタートし、2012年には東急直通線の計画も発足しました。私たち相鉄グループにとっては、この「都心直通」は非常に重要なチャンスです。「沿線の都市開発についてもぜひ力を入れていきたい」ということで、さまざまな関係者のみなさまとともに開発の準備を進めてきました。
宮本:横浜国大さんとの連携が始まったのは、駅周辺の開発を進めていく過程で、市の諮問機関である横浜市都市美対策審議会に相談したことがきっかけでした。委員の方に「横浜国大さんは地域の資源なのだから、きちんと連携しながらまちづくりをしていったほうがいい」と助言をいただきました。そこから横浜国大さんと寺田倉庫さんと一緒に大学連携の進め方について相談を行い、平成28年3月に策定した地区計画の中で、「建築物には周辺地域の特性である農業や大学の活動を支援する施設等を導入する」と位置付けることができました。
──ありがたいお声がけだったのですが、本学にある20を超える地域課題実習のなかで、農業を扱うものは1つだけだったのです。それだけではスペースを持て余してしまうということで、最終的には「地域課題実習全般や研究、ワークショップなどに幅広く活用する」という方針に変更していただきました。
高見澤:結果的に、活用の幅が広がって良かったのではないかと思います。当時の会議で覚えているのは、間に入っていただいた各社の担当者様のなかに本学の卒業生の方が多かったことです。お互い勝手がわかっているからか、意識合わせもスムーズに進みました。
田嶋:地域や大学の事情に通じている担当者が多かったのは、私たちにとっても非常にありがたかった部分です。思わぬところで「地域にとって、いかに大学が大きな存在なのか」を実感しました。
──ところで、駅名に「横浜国大」を入れていただいた経緯についてご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。実は私たちも、正確な背景については知らされておらず……。
齋賀:私も当時の社内事情をすべて把握しているわけではありません。ただ、やはり羽沢地区の新駅構想が進む段階で、「横浜国立大学」が地元のブランドとして大きな意味を持ったのだろうと思います。相鉄グループとしても、「羽沢」だけではイメージが掴みにくいので、駅名に何か付加価値をつけたいという意図があったはずです。結果的に横浜国大の名前が入ったことで、知名度はぐっと上がったのではないかと。
高見澤:そんな風に思っていただけるのは本当にありがたいことですし、「地域あっての大学」だとあらためて思います。また、本学の名前が駅名に入ったことで、学内でも羽沢地域に関する取り組みに注目が集まりやすくなっているのも事実です。この恵まれた状況を、ぜひ活かしていきたいですね。
市民と大学をつなぐ「ハブ」として
──続いて「YNU BASE HAZAWAをどのように活用していきたいか」について、みなさんのご意見を伺えればと思います。
高見澤:現状行われている取り組みとしては、学生たちが地域住民向けのイベントを開催してくれています。たとえば「BOSAIラボ」という地域課題実習では、防災に関するワークショップを行ったそうです。こうした取り組みをキャンパスの外で行えるのは、学生にとってもよい機会になりますね。
佐藤:地域住民と学生のみなさんが交流する取り組みは、神奈川区としても非常にありがたいです。新駅が誕生し、マンション開発などが進んでいくと、新しい住民の方も地域に増えていきます。新旧住民の交流の機会も積極的に作っていけたらと考えていますが、その時には横浜国大の学生さんにもぜひご参加いただきたいなと。
──先の会議でも、まちづくり分野の先生方から「学生の活動はさまざまな属性の地域住民をつなぐハブになる」という意見が出ていましたね。ちなみに地域行政の観点から、本学やYNU BASE HAZAWAに対して「こういう取り組みを行ってほしい」といった要望はございますか。
佐藤:地域にとって、学生のみなさんの「若い力」には大きな意味があります。大学の拠点が駅前にあるということ自体が、区民にとってプラスになると思っています。
事実、すでに私の部署からも「ワークショップを行う会場として使えないか」「小学校の取組に関して展示を行えないか」といったお問い合わせを、YNU BASE HAZAWAにさせていただいているようです。学生さんと地域との接点には、強いニーズがあるということですよね。
田嶋:「HAZAAR」にはマンションも併設されており、すでに新たな住民の方々がたくさん移り住んでいます。せっかく同じ建物ですので、YNU BASE HAZAWAに足を運んでいただけるような交流イベントなどを企画していきたいですね。
──昨年10月のオープニングイベントでは、野菜から抽出した色素をつかった絵具で布に色付けを行う「やさい色ワークショップ」が実施されたのですが、まさにマンションにお住まいのお母さん方がたくさん覗きに来てくださいました。親子連れの方でも参加できるイベントを実施すると、地域のみなさんをうまく巻き込んでいけるのかもしれません。
高見澤:別のエリアで地域活性の取り組みを行ったときに、一番有効だったのは「その地域のまちづくりについて話し合い、情報交換する場を定期的に持つ」ことだったんです。異なる立場同士で集まり、同じ目線で意見を交わすだけで十分に意味があるということですね。それはこの羽沢地区も例外ではないはず。まずは産学官民で顔を合わせて話をする。そのために、新たな拠点を設けたわけですから。
「羽沢発」の新研究にも期待
宮本:YNU BASE HAZAWAについては、「大学の研究を地域に開く」役割にも期待しています。昨年11月に開催された「羽沢バレーで半導体!横浜国大の半導体の取り組みを紹介」という企画に参加させていただき、半導体・量子集積エレクトロニクス研究センターの井上史大准教授とお話しすることができました。また、別の機会に同研究センターの真鍋誠司教授ともお会いすることができ、この羽沢地区をシリコンバレーにならい、「羽沢バレー」と位置付けていきたい構想も伺いましたので、今後も地域の方々が研究に触れられる場を作っていただけたらと思っております。
高見澤:交通の不便さ、農地や緑地の保全、人口動態の偏りなど、いわゆる「地域課題」もたくさん残されているエリアです。研究者としては、むしろそれを活かして新たな研究を生み出してもらいたい。社会実装やフィールドワークの拠点として、このYNU BASE HAZAWAを活用してもらえたらと思います。ここが産学官民連携のハブとしてうまく機能すれば、いずれ「羽沢モデル」の新たな研究が誕生するかもしれませんね。
田嶋:個人的には、正規の授業や研究プログラムだけでなく、サークルや部活などの自由な取り組みがこの場から始まるのを楽しみにしています。私たちは、新駅開業以来「ハザコクフェスタ」や「HAZAWA VALLEY FES 2023」など地域と連携したイベントを開催してきました。昨年の「HAZAWA VALLEY FES 2023」のアメリカンフットボール部のチアリーディングパフォーマンスは好評でしたし、今後も音楽系サークルや芸術系の学部の方々など、いろいろな学生さんに集まってもらえたら、この新街区にも活気が生まれそうだなと。
特に横浜国大さんにも引き続きご協力いただきつつ、今後は近隣の小中学校や教育機関も巻き込みながら、賑やかな街を作り出していけたらと考えています。
地域と大学が「ともに考える場」をつくる
──最後に、今後のまちづくりの方向性と、YNU BASE HAZAWAに期待する役割について伺えればと思います。
宮本:横浜市としては、この駅周辺地区を含む「新横浜都心」エリア全体を、より魅力ある地域にしていくのがミッションです。特に羽沢地区に関しては、羽沢横浜国大駅が開業したことを契機とし、賑わいを生み出すと同時に、「地域特性である農地や自然をいかに保全し、有効活用していくか」についても考えていく必要があります。
この点については、大学の研究や学生の力を借りながら、新技術を活用した農業や、スマートモビリティ、防災など、さまざまなアプローチを探っていきたい。YNU BASEには、そうした 「新しい取り組み」を形にしていくための拠点になってほしいと期待しています。
高見澤:都市計画や地域連携に携わってきた人間として思うのは、この地域は非常にポテンシャルが高いということです。緑も多いし、大学も、古くからの街並みもある。足りなかったのは、人が集まってコミュニケーションできるような場です。今回の拠点や商業施設のオープンによって、この街はどんどん面白くなっていくはず。あとは今回の座談会のように、なるべく多様な立場の人間が集まり、主体的に街を作っていけたらと思います。
佐藤:神奈川区は、2027年に区制100周年という大きな節目を迎えます。「次の100年」のための周年事業ということで、区としても力を入れて準備をしていきます。また、同年に「GREEN × EXPO 2027」の開催も控えておりますので、脱炭素やまちづくり、農業といったテーマの取り組みも増えていくはずです。そのような機会に、YNU BASE HAZAWAや横浜国大さんとの連動企画が実施できれば、さらに魅力が広がるのではないかと期待しております。
齋賀:私たち相鉄グループとしては、「大学が駅前に拠点を構えていること」そのものが、街の魅力を高めるうえで重要だと考えています。学生のみなさんに日常的に行き来してもらえれば商業施設も活性化しますし、新住民や移住検討者も「若く活気にあふれる街」として安心感を持ってくださるはず。YNU BASE HAZAWAがその象徴となってくれたら嬉しいですね。
田嶋:賑わいの創出は、マンションや商業施設の価値向上にも直結します。テナントや住民の皆さんに「ここに住んで良かった」、「出店して良かった」と感じてもらえるまちづくりをしていくことが、我々にとっても大切です。
大学の拠点が「閉じた研究室」になってしまっては意味がありません。この場所が日常的に学生や住民の方々に利用していただける「オープンな場」になるよう、引き続きサポートしていきたいです。
──ありがとうございます。大学としては、まず学内でYNU BASE HAZAWAの認知度を高めていきたいですね。今でも「こんなに便利な場所があるなんて知らなかった」という声を聞きますし、「どう使っていいかイメージが湧かない」という教員もいる。地域連携に関する取り組みに限らず、あらゆる学部・研究室から「使ってみたい」と思ってもらう必要があります。
高見澤:新しい街、新しい駅、新しい拠点──。あらゆるものが「これから」に向けて動き出している段階です。大学としても、ここでしかできない学びや研究が必ずあると思いますし、それが地域の方々に役立つ形になれば理想的です。今後もみなさんと手を取り合い、新たな街を盛り上げていきたいですね。
地域連携コーディネーター(末尾コラム)
YNU BASE HAZAWAでは、本学と地域をつなぐ役割として2名の「地域連携コーディネーター」を配置しています。本施設や地域連携推進機構宛にいただいたお声がけやご要望を踏まえ、担当コーディネーターが具体的なイベント企画や地域交流などを推進する仕組みとなっています。
2名の「地域連携コーディネーター」は、いずれも都市に関わる専門性を有し、より住民の方々に近い目線で地域の声を拾い上げ、施策に反映していきます。専任担当者として大学と地域の間に入ることで、連携や企画がスムーズに進むよう期待されています。
(担当:地域連携推進機構)
公開日:2025.03.26
-
 第10回
第10回新しい駅を、新しい「まち」に。「YNU BASE HAZAWA」からはじまる産学官民の挑戦
公開日:2025.03.26 -
 第9回
第9回関内のポテンシャルを解き放て!
まちづくりのエキスパートを育む「アーバニストスクール」公開日:2024.03.26 -
 第8回
第8回「新湘南」を世界に誇れるまちに!ヘルスイノベーション最先端拠点形成に向けた産官学医連携プロジェクト
公開日:2023.03.28 -
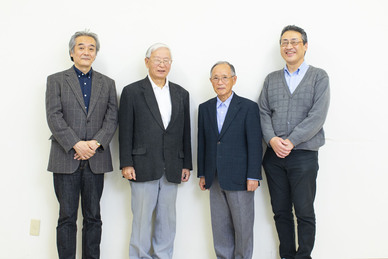 第7回
第7回住民発の「まちづくり」に挑戦! 「羽沢横浜国大駅」周辺住民がバリアフリー基本構想作成を提案
公開日:2022.01.19 -
 第6回
第6回保育園の音環境を改善したい! 帝人フロンティア株式会社、星川ルーナ保育園とともに挑んだ共同研究
公開日:2021.02.04 -
 第5回
第5回野菜の鮮度が「見える」アプリ! 横浜銀行と地域農業の振興に向けた取り組みがスタート
公開日:2021.01.07 -
 第4回
第4回世代を超えた地域交流を進めたい!旭区・左近山団地に住む学生たちが考えるまちづくり
公開日:2020.01.31 -
 第3回
第3回箱根町の経済循環の「見える化」にチャレンジ!7人の学生がビッグデータと実地調査で分析
公開日:2020.01.31 -
 第2回
第2回保土ケ谷区の子どもと1年間全力で遊ぶ!「がやっこ探検隊」が育む地域の絆
公開日:2020.01.31 -
 第1回
第1回金太郎だけじゃない!学生が南足柄市の魅力を「ビジネスプラン」で提案
公開日:2020.01.29