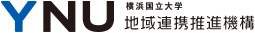NEWS & EVENTS
2018年度 横浜国立大学地域連携シンポジウムを開催しました

2019年2月15日(金)14時半から、横浜情報文化センター6階の情文ホールで『2018年度 横浜国立大学地域連携シンポジウム』を開催しました。
プログラムの前半は、19グループの学生たちが「地域課題実習」の成果を報告。中間にラウンジでのポスター発表と投票をはさみ、後半はパネルディスカッション、そして最後にアワードの表彰式を行いました。
プログラムの前半は、19グループの学生たちが「地域課題実習」の成果を報告。中間にラウンジでのポスター発表と投票をはさみ、後半はパネルディスカッション、そして最後にアワードの表彰式を行いました。
学生たちの工夫あふれる発表の数々

シンポジウムの幕開けは、中村文彦理事の開会の挨拶です。
学生たちの地域連携の活動にサポートくださっている方々への感謝と、シンポジウムでの充実した学びへの期待が述べられました。
学生たちの地域連携の活動にサポートくださっている方々への感謝と、シンポジウムでの充実した学びへの期待が述べられました。
プログラム前半の「地域実践アワード2018」では、「地域課題実習」の19グループがそれぞれの活動について発表しました。
地域のさまざまな課題解決に取り組む「地域課題実習」は、横浜国立大学の学生の7.3%が受講するカリキュラムです。
中には、先輩から後輩へと熱心に受け継がれている取り組みもあります。
発表の持ち時間は各グループ3分。短時間での凝縮したプレゼンテーションが続きました。
※各グループの活動報告についてはこちら(報告書PDFファイル)
地域のさまざまな課題解決に取り組む「地域課題実習」は、横浜国立大学の学生の7.3%が受講するカリキュラムです。
中には、先輩から後輩へと熱心に受け継がれている取り組みもあります。
発表の持ち時間は各グループ3分。短時間での凝縮したプレゼンテーションが続きました。
※各グループの活動報告についてはこちら(報告書PDFファイル)


発表終了後、2名のゲスト審査員から講評をいただきました。「地域実習の良さは、教室で学んだことを活用し、地域といっしょに課題解決に活かせることにある」「自分たちができる小さなアイディアを実現していくことが大切」など、学生たちの活動にエールが送られました。ゲストの依田さやか氏は本校の卒業生でもあり、世界銀行の東京防災ハブに勤められています。また、秋元康幸氏は長年横浜市役所に勤め、2018年度から本校の地域連携推進機構客員教授として教鞭をとっています。
その後、ホール脇のラウンジスペースに場所を移し、約30分間の「地域連携ディスカッション」を行いました。
限られた時間でしたが、周囲に展示された各グループのポスター発表を見ながら活発な交流が広がっていました。
そして、参加者それぞれが特に評価するグループを投票用紙に記し、アワード選出のための一票を投じました。
その後、ホール脇のラウンジスペースに場所を移し、約30分間の「地域連携ディスカッション」を行いました。
限られた時間でしたが、周囲に展示された各グループのポスター発表を見ながら活発な交流が広がっていました。
そして、参加者それぞれが特に評価するグループを投票用紙に記し、アワード選出のための一票を投じました。


地域連携の可能性を探るパネルディスカッション

後半は、「ヨコハマ・かながわの潜在力を活かした地域連携を探る」と題したパネルディスカッションを行いました。
基調報告「横浜国立大学の地域連携の現状と課題」(高見沢実学長補佐)を受けて、本校の卒業生でもある伊藤暁建築設計事務所の伊藤暁氏から「寛容さがもたらす持続性~神山町の事例」の報告がありました。過疎化が進み高齢化率の高い地域ですが、町民自身が「楽しい」と感じることの実践を積み重ねる「創造的過疎」の試みが展開されていて、伊藤氏自身も楽しみながら地域に貢献している姿が伝わってきました。
続いて事例紹介。1つめは、箱根町企画観光部企画課の伊藤和生副課長の「箱根町の大学連携の取り組み」です。財政に大きな課題を抱える町の「新財源確保有識者会議(2015)」に本学の伊集守直教授が委員として参画したことから連携が始まります。2017年からは「行政運営を考えるための町民会議」に池島祥文准教授がアドバイザーとして加わり、調査研究がスタート。2018年2月に包括連携協定が締結された流れが紹介されました。2つめは、横浜国大校友会評議員・富丘会理事長の宮田芳文氏から「地域から大学と連携するということ」と題して、横浜を拠点とする企業28社の参加のもと「YNU横浜経営者の会」を組織し、地元に目線を向けて、2017年から勉強会を定期的に開催していることなどが報告されました。
続くディスカッションでは、「活動は息長く続けていくことが大切」「人のためにやるのではなく、オープンなつながりの中で自分のためにやることが大切」「いろいろな楽しみがあることに気づくのが、連携のポイント」「大学の研究成果をもっと発信すれば、連携の可能性が広がる」などの意見が活発に交換されました。
基調報告「横浜国立大学の地域連携の現状と課題」(高見沢実学長補佐)を受けて、本校の卒業生でもある伊藤暁建築設計事務所の伊藤暁氏から「寛容さがもたらす持続性~神山町の事例」の報告がありました。過疎化が進み高齢化率の高い地域ですが、町民自身が「楽しい」と感じることの実践を積み重ねる「創造的過疎」の試みが展開されていて、伊藤氏自身も楽しみながら地域に貢献している姿が伝わってきました。
続いて事例紹介。1つめは、箱根町企画観光部企画課の伊藤和生副課長の「箱根町の大学連携の取り組み」です。財政に大きな課題を抱える町の「新財源確保有識者会議(2015)」に本学の伊集守直教授が委員として参画したことから連携が始まります。2017年からは「行政運営を考えるための町民会議」に池島祥文准教授がアドバイザーとして加わり、調査研究がスタート。2018年2月に包括連携協定が締結された流れが紹介されました。2つめは、横浜国大校友会評議員・富丘会理事長の宮田芳文氏から「地域から大学と連携するということ」と題して、横浜を拠点とする企業28社の参加のもと「YNU横浜経営者の会」を組織し、地元に目線を向けて、2017年から勉強会を定期的に開催していることなどが報告されました。
続くディスカッションでは、「活動は息長く続けていくことが大切」「人のためにやるのではなく、オープンなつながりの中で自分のためにやることが大切」「いろいろな楽しみがあることに気づくのが、連携のポイント」「大学の研究成果をもっと発信すれば、連携の可能性が広がる」などの意見が活発に交換されました。
同票で複数表彰が多かったアワード
パネルディスカッションが終わると、いよいよアワード表彰の発表です。「校友会賞」には、同票数で2チームが選ばれました。
「現代世界の課題の探索と協力の実践 -ネパール支援プロジェクト-」と「ローカルなマテリアルのデザイン」の2チームです。
「準MVP賞」は、やはり同票数で3チームが受賞しました。
「現代世界の課題の探索と協力の実践 -ネパール支援プロジェクト-」
「おおたクリエイティブタウン研究プロジェクト」
「ローカルなマテリアルのデザイン」
の3チームです。
そして「MVP賞」を勝ち取ったのは、「アグリッジ商品開発」のチームでした。


「アグリッジ商品開発」チームは、農産物の販売と農産加工品の開発に行き詰まり、ニーズがあるのは農産加工品の販売促進であるという結論に達して方向を転換。地域の食品加工業者が製造する梅ジュレやピクルスなどを常盤祭で販売して成果を出しました。

シンポジウムの最後の挨拶は、長谷部勇一学長です。
実践性は大学の柱のひとつであること、「自分ごととして考える」が大切なキーワードであること、そして東京に隣接する神奈川の潜在力を活かして地域の循環を活性化させる戦略が必要だということを、シンポジウムを通してあらためて実感できたと総括されました。YNU地域連携推進機構が核となり、大学が研究面でも地域との連携を行い、ローカルな知見をグローバルに役立てていきたいというビジョンも述べられました。
当日の様子は、本学公式Youtubeチャンネル でご覧いただけます。
でご覧いただけます。
実践性は大学の柱のひとつであること、「自分ごととして考える」が大切なキーワードであること、そして東京に隣接する神奈川の潜在力を活かして地域の循環を活性化させる戦略が必要だということを、シンポジウムを通してあらためて実感できたと総括されました。YNU地域連携推進機構が核となり、大学が研究面でも地域との連携を行い、ローカルな知見をグローバルに役立てていきたいというビジョンも述べられました。
当日の様子は、本学公式Youtubeチャンネル